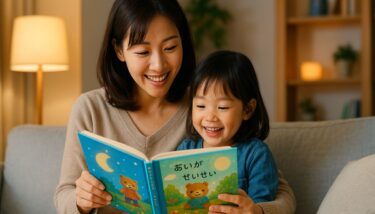「今日のお話、どんなお話がいい?」
そんな問いかけに、子どもが「恐竜が宇宙に行く話!」と答えたら――
次の瞬間、その物語が絵本になって手元に届く。
そんな魔法みたいな体験が、もう夢じゃなくなってきています。
しかもそれを実現してくれるのは、人間の作家さんではありません。
AI(人工知能)が物語を考え、絵を描き、世界にひとつだけの絵本をつくってくれるんです。
最近では、絵本を“読む”だけでなく、子どもの性格や興味に合わせて“作る”という新しい楽しみ方が注目されています。
たとえば、動物が好きな子には動物が主人公の話。内気な子には、自信を持てるような勇気のお話。
そんなふうに、子どもにぴったりのストーリーが、AIの力で生まれるんです。
この記事では、AI絵本ってどんなもの? という基本から、使い方、親子のふれあい、教育の可能性まで、やさしくご紹介していきます。
ちょっとワクワクしてきた方、どうぞこのまま読み進めてみてくださいね。
AIが絵本を作るってどういうこと?
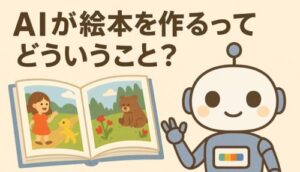
「AIが絵本を作る」と聞いても、ちょっと想像しにくいかもしれません。
でも実は、もうすでにその技術は私たちのすぐそばまで来ているんです。
AIが絵本を作るとは、文章の生成・イラストの作成・デザインの構成など、絵本に必要なすべての要素をAIが自動でやってくれることを指します。
たとえば、ある子どもが「海の冒険が好き」と入力したとします。するとAIはそのキーワードに合わせて、ストーリーを考え、登場人物をつくり、ページごとの展開を組み立て、イラストまで描いてくれるんです。
この技術の中心にあるのが、生成AI(Generative AI)と呼ばれるしくみです。
言葉や絵を“自分で考えて作り出せるAI”で、最近はChatGPTや画像生成AIなどでも話題になっていますね。
この生成AIが、物語の構成や絵のタッチなどを学習しながら、オリジナルの絵本を生み出してくれるわけです。
さらに最近では、アプリやWebサービスとして気軽に使えるツールも増えてきています。
たとえば、名前を入力するだけで「○○ちゃんが主人公になる冒険絵本」を作ってくれるサービスも登場していて、親子で楽しめるコンテンツとして注目されているんですよ。
つまり、AI絵本とは「決まった物語を読む時代」から、「自分のために作られた物語を体験する時代」への大きな一歩。
世界にひとつだけの絵本が、ぐんと身近になってきたんです。
アプリ、WEBサービス一覧(2025年5月時点)
| サービス名 | 特徴 | 利用方法 | 対象年齢 | 価格帯 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| AIえほん図書館 | 対象年齢・主人公・テーマを選ぶだけで、AIがストーリーとイラストを自動生成。親子の読み聞かせに最適。 | Webブラウザ/アプリ(iOS・Android) | 赤ちゃん〜小学生 | 基本無料(有料版あり) | https://app.ehonlib.com/signup?f=pr01 |
| はじまりはじまり | 子どもが選んだ選択肢からAIが物語を生成。音声ガイド付きで未就学児でも操作可能。 | Webブラウザ対応 | 乳児〜小学校低学年 | 月額990円〜 | https://www.hajimari.app/ |
| おぼえたことばのえほん | 子どもが覚えた言葉を入力すると、AIが関連ワードを使って物語を生成。言語習得のきっかけに。 | Webブラウザ対応 | 1歳〜 | 無料(期間限定公開) | https://ai-ueo.jp |
| 絵本メーカー | オリジナルの絵本を作成できるWebアプリ。ファミリーデーなどの記念に最適。 | Webブラウザ対応 | 幼児〜 | 無料 | https://techceed-inc.com/engineer_blog/12137/ |
| ReadKidz絵本 | AI技術を駆使して、専門知識がなくても高品質な絵本を作成可能。親子での創作体験に最適。 | Webブラウザ対応 | 幼児〜 | 無料〜 | https://wzz.co.jp/ai_lab/readkidz-ai-ehon-easy-guide/ |
子どもの性格に合わせてストーリーが変わる?

「うちの子、ちょっとシャイで……」「冒険ものが大好きなんです!」
そんな声に、AI絵本はしっかり応えてくれます。実は今の生成AI絵本サービスは、ただ物語をつくるだけでなく、子ども一人ひとりの性格や好みに合わせてストーリーを“変えてくれる”んです。
たとえば、元気いっぱいな性格の子には、スピード感のある冒険ストーリー。
逆に、優しくて思いやりのある子には、動物たちと助け合う心あたたまる物語。
「恥ずかしがり屋だけど、ヒーローになりたい!」そんな子には、自信を持てるように成長していく主人公が登場する絵本が生成されるなど、AIは言葉のヒントから性格を読み取り、感情に寄り添った物語を届けてくれるのです。
最近のサービスでは、性格診断や好きなキャラクターを選ぶだけで、ぴったりの展開にカスタマイズしてくれるものも増えています。
たとえば「えほんAIメーカー」では、名前・年齢・好きなものを入力すると、「○○ちゃんが宇宙を旅する話」や「動物の村を救うお話」など、子どもが主人公になる絵本がすぐに完成します。
このように、“読者に合わせて物語が変わる”という体験は、紙の絵本ではなかなかできないこと。AIだからこそ実現できる“あなただけの物語”が、子どもたちの心に深く残るのです。
そして何より大切なのは、「自分が主人公だ」という実感。この体験が、子どもの自信や想像力、そして表現力を自然に育んでくれるんですよね。
AI絵本が育てる「想像力」と「親子の絆」

「ママ、つぎはどんなお話が出てくるのかな?」
そんな声が、AI絵本を開くたびに聞こえてくるようになります。
AIでつくる絵本は、ただ読むだけのものではなく、“一緒に楽しむ時間”そのものを生み出すツールなんです。
まず注目したいのが、子どもの想像力への働きかけです。
AIが作る物語は、子どもの好みや性格に合わせて内容が変わるので、先の展開が読めません。毎回違うストーリーに出会えることで、「次はどうなるんだろう?」と想像をふくらませる力が自然と育まれます。
また、自分の名前が登場したり、好きな動物が主人公になったりすることで、物語の世界に入り込みやすくなるのも大きなポイントです。
そしてもうひとつ大きな魅力が、親子のコミュニケーションが増えること。
たとえば、物語の途中で「このあと、○○ちゃんはどうすると思う?」と問いかけたり、読み終えたあとに「どこが面白かった?」と感想を共有したり。
AI絵本は“話すきっかけ”を自然に生み出してくれるんですね。
絵本の読み聞かせって、親にとっても癒しの時間。
毎日が忙しくても、「今日も一緒に読もうか」と、ほんの10分のふれあいが心をつなげてくれます。
AI絵本は、その時間をもっと豊かに、もっと個性的にしてくれるパートナーなのです。
想像の世界を一緒に旅すること。それが、子どもの心を育て、親子の絆を深める最高の時間なのかもしれません。
使い方はかんたん?どんな家庭でもできる?

「AI絵本って便利そうだけど、なんだか難しそう…」
そんな不安を感じる方もいるかもしれません。
でもご安心ください。最近のAI絵本サービスは、パソコンやスマホがあれば誰でもすぐに始められるように作られているんです。
たとえば多くのサービスでは、最初に子どもの名前、年齢、好きなものをいくつか入力するだけ。
「恐竜が好き」「お姫さまが好き」「ピンク色が好き」といった情報を選ぶと、AIがそれに合ったストーリーを考えてくれます。さらに、好みに合った絵のテイストまで自動で合わせてくれることも。
難しい操作は一切不要で、スマホひとつで完結できるサービスもたくさんあります。
中には、音声ガイド付きで読み聞かせまでしてくれるものもあり、文字が読めない年齢の子どもでも楽しめるよう工夫されているんですよ。
印刷して製本できるタイプもあり、プレゼントや記念品として残すことも可能。誕生日や入園祝いとしても人気が高まっています。
また、アプリやWebサービスの多くが無料または低価格で利用できるので、家計の負担にもなりにくいのがうれしいポイント。
「ちょっと試してみたいな」という方でも気軽に始められる設計になっているんです。
つまり、特別なスキルや機材はいっさい不要。
スマホを開いて数分で、子どもだけの特別な絵本が完成する。
それが、今のAI絵本の世界なんです。
どんな家庭でもすぐに楽しめるこの体験、きっとあなたの生活にも新しいワクワクを届けてくれるはずですよ。
ChatGPTでAI絵本を作りたいときのプロンプト例
実は、ChatGPTを使ってもオリジナルの物語や絵本のアイデアを簡単に作ることができます。
以下は、初心者でも使いやすいプロンプトの一例です。
| 以下の条件で、子ども向けのオリジナル絵本のストーリーを作ってください。 【条件】 |
このように入力すれば、ChatGPTがストーリーを考えてくれます。
さらに、「ページごとにセリフも入れて」「登場キャラをもっと増やして」などと追加指示を出すことで、どんどん自分だけの絵本にアレンジしていくことができます。
未来の読み聞かせ:AI絵本が教育にもたらす変化

「読み聞かせ」は、これまで家庭の中で行われるものというイメージが強かったかもしれません。
しかし今、AI絵本の登場によって、その役割は家庭から“教育の現場”へと大きく広がり始めています。
たとえば、保育園や小学校では、子どもの性格や発達段階に合わせた絵本の選定が求められます。
ここでAI絵本が活躍します。教師や保育士が子どもの興味や性格を簡単に入力するだけで、個別最適化された絵本を作ることができるからです。
さらに、多様性を尊重する教材としての活用も進んでいます。
国籍や文化、家族の形が多様化する中で、画一的な内容の絵本では子どもが共感しにくいことも。
AI絵本なら、その子の背景に合わせたキャラクターやストーリーを生成できるので、誰もが「自分らしさ」を大切にできる読書体験が可能になります。
また、発達支援の現場でもAI絵本は注目されています。
視覚に訴えるイラスト、音声読み上げ機能、簡単な操作性など、読み聞かせが苦手な子どもや言語発達に課題がある子にも対応できる点が高く評価されているのです。
教育の中で大切にされている「非認知能力」――想像力、協調性、自己肯定感などは、まさに絵本を通して育まれる力。
そこにAIが加わることで、すべての子どもが物語を通じて“学びを楽しめる”未来が、すぐそこまで来ています。
まとめ
絵本といえば「読むもの」という時代は、いま大きく変わりつつあります。
AIによって作られる“世界にひとつだけの物語”は、子どもにとって特別な体験となり、親子にとってもかけがえのない時間を生み出してくれます。
しかも、使い方はとてもシンプル。スマホやパソコンがあれば、誰でも手軽に始めることができます。
子どもの性格や興味に合わせて内容が変わることで、想像力や表現力、そして自己肯定感を自然に育むことができるのも大きな魅力です。
これからの絵本は、家庭だけでなく、教育や支援の現場にも広がっていくことでしょう。
AI絵本は「物語を届ける」だけでなく、「心を育てるツール」へと進化しているのです。
さあ、あなたも今日から、あなただけの絵本の扉をひらいてみませんか?